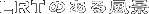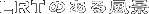| <記事内容>
欧州に何十年も遅れ
福祉の先進地といわれるヨーロッパの街々を歩いて日本に帰って気が付くことは、わが国では歩道上に妙に誘導ブロック(点字ブロック、点字タイル)が多いことであった。
「環境施策ウォッチング」の旅は、スイス・バーゼル市を起点に、短期間に南西ドイツのフライブルク、東仏ストラスブール、再びドイツに戻りカールスルーエ、マンハイムなど合計9都市を若者たちと鉄道のみで移動した。
各都市で私たちの目を奪ったのは、先進的なハイテク低床式路面電車(LRT)が滑らかに走るトランジットモールであった。
ヨーロッパでは障害者が介助者なしに独自に街へ出掛けることを可能にするための努力が払われた歴史と実績がある。低床式のLRTやバスは、そのような努力の一つの成果であり、路面からの床高が20数cm。電停(バス停)の安全地帯の高さをそろえておけば、車イス利用もベビーカーの若い母親も極めてスムーズに乗り降りができる。
しかしながら、それらの街でも、すべてが低床式車両というわけではなく、目下は過渡期であり、従来型のステップを上り下りしなくてはならない車両もまだたくさん残っている。
私たちを感動させたのは、LRTの素晴らしさだけではなく、従来型の車両で見掛けた数々のシーンであった。ステップに高齢のおばあさんが近づいた時、ベビーカーを押す若い母親が下車しようとしたとき、車イスの青年が乗り込もうとしたとき、一瞬のためらいもなく、とても自然に周囲の人間が歩み寄り手を貸す。腰の軽さ、タイミングも絶妙に思えた。
バリア・フリーとは、物理的な環境の整備は無論だが、それ以上にあるいはそれ以前に何が必要かを見せられる思いであった。
「ハートビル法」が施行され、静岡県でも「福祉のまちづくり条例」により、整備が進められている。そして冒頭の話に戻るのだが、安心して歩けるゆったりした歩道や自転車道のネットワークの整備という点でヨーロッパに何十年も遅れている観のある、わが国で、視覚障害者用の点字ブロックのみが各地の施設で整備され、妙に目立っている。
視覚障害者の方の話によると、かえって危険な設置例もあるという。また私の観察した範囲で、不可解な整備に見える例もある。
県立美術館とそのプロムナードは、建築でも都市景観でも複数の受賞歴のある格調高い雰囲気の漂う一画である。そんな施設のバリア・フリー化整備が済んだ際、県のボランティア協会主催のバリア・フリー調査に参加し、正直のところ頭を抱えた。
外部に設けた合成ゴム製の点字ブロックが延べ418m。尋常な数字ではない。正面アプローチの何ヵ所もある階段を視覚障害者が上がってくることを想定してのことのようだが、このアプローチは障害者には厳し過ぎないか?
点字ブロックを縦横に整備すればそれは優しい配慮といえるのだろうか?
正面玄関の右、バスの終点側には車イス利用者の駐車場とスロープが用意されている。視覚障害者のアプローチもこちらに想定すれば、玄関までの歩行ルートに階段などの障害物はなく、その方が親切な配慮ではないか?障害者用サインもスロープの存在を示す最小限の点字ブロックだけで済む。
美しいものを展示し、県民の美意識をリードすべき施設のアプローチが、黄色のゴム製点字ブロックを敷設したことで、その美しさが損なわれたことにも心痛むものがある。 |